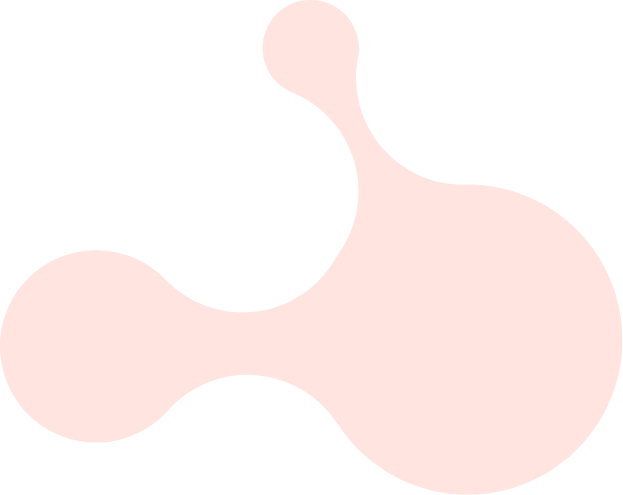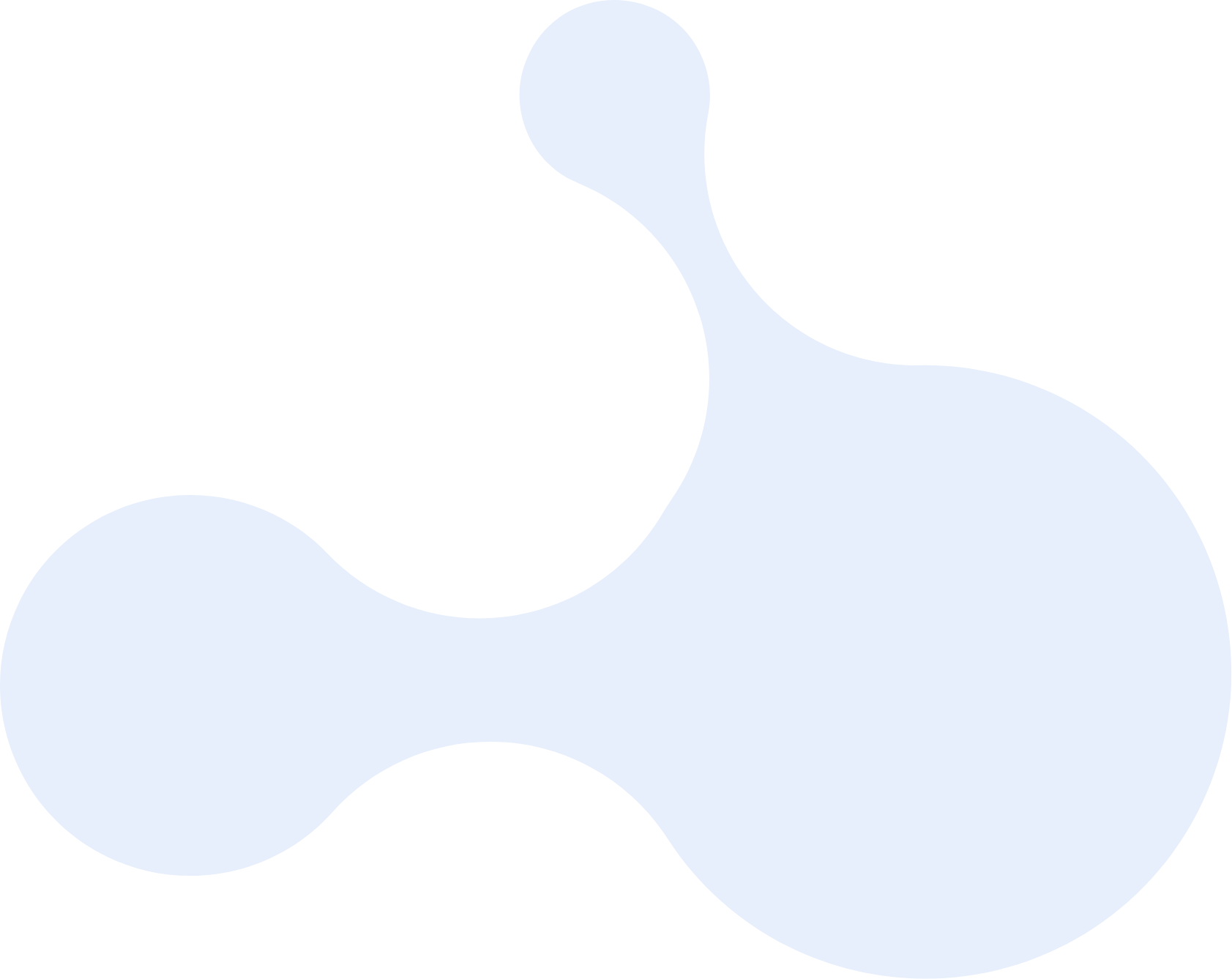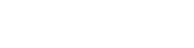手を動かすと見えてくる! あなたのためのアイデア発想28

こんにちは。ホンブチョウです。この連載コラムでは私が今まで学んできたアイデア発想のやり方を毎回ひとつづつ紹介していくことで、あなたに合ったやり方を見つけてもらいたいと考えています。
第二十八回は、
プロトタイプ発想法
先日、武蔵野美術大学が主催した「VCP for PROTOTYPING体験会」というものに参加してきました。いろいろと気づきのある楽しい体験会でしたが、今回はそこでの気づきからの発想法です。
当日、自己紹介がてら早速、あるものを形にするというところから始まったワークショップでしたが、「手を動かすと何がおもしろいか?が、見えやすい」という基本的なことに立ち返らせていただけるような時間でした。
また、まさにそうだよね!と共感できたのは青木俊介教授が話された
「アイデアはかよわい」というひと言でした。
確かにアイデアというのは、儚くかよわく、実現しないままに、すぐに他者のネガティブなコトバやマイナスな意見、また自分自身にも簡単にあきらめられ、埋もれていく場合がほとんどです。「人はダメな理由はいくらでも思いつく」というお話も講義の中で出ましたが、アイデアを拡げて、縮めて、また拡げてとしていく中で、捨てられていくアイデアの中に本当はすごいアイデアの種があったのに!ということも多々あるように思います。アイデアを選ぶ基準みたいな話もいずれしたいとは思いますが、今回のプロトタイピングもアイデアを選ぶ基準となり得るひとつの方法だと私は思います。
人には、直感やイメージを好むタイプの方と、数字や論理を好むタイプの方がいるように、なかなか思いついたアイデアを他者に伝えるにはハードルが高く、いくら言葉を尽くしても、なかなか伝わりづらくコミュニケーションギャップが起こる場合も多いです。
そんな時にプロトタイプを作るということは、自分自身のアイデアをブラッシュアップしたり、あきらめることを思いとどまらせたり、バイアスをとっぱらったり、そしてなにより人に伝えるための大きな武器になります。
では、やり方を見てみましょう。今回は例えば新しい玩具を開発したい!としてみましょう。
1. まずは、今までこの連載でいろいろ試してきたような発想法を使って、あなたの作りたい玩具を考えてみてください。もちろんこのコラムで何度も伝えているように、くだらないものでも、妄想でもOKです。今回は玩具なので、自身の心の中の子供の頃の声に従ってみてください。
例えば初めの頃にやった「SCAMPER」とか「カラーバス」などは合うかもしれません →
2. できれば、その時、複数人で取り組むことをお勧めします。当然のことながら人それぞれ全く違う玩具をイメージすることでしょう。Aくんは犬と遊ぶ玩具、Bさんは子供たちみんなで遊ぶ玩具、Cさんは大人向けのホビー玩具というように。でも人の意見には自分には気づけなかった視点や、共感できるところなどが必ず含まれています。
3. つくりたい玩具のアイデア(自分の案、でもチームの案でも結構です)を、発想のまま終わらせないぞ!という気持ちで3つの方向でアプローチしてください。
-
「デザイン的」なプロトタイプアプローチとしては、見た目や手触り感、形などがバックリ再現できていれば良しです。こだわることも大事ですがあまりそこに時間をかけすぎるのはアイデア発想視点ではあまり必要ないと思います。昔は試作品を作るとなると、かなりコストも時間もかかり、大変な作業でした。しかし今は100均もあれば3Dプリンターもあります。昔に比べれば格段に安く、短時間でプロトタイプを作れるようになっています。
-
「機能的」なプロトタイプアプローチとしては、動きや体感できることを再現します。簡易なプログラミングツールなどを利用しても良いでしょうし、中身は空っぽで手動で動かしても構わないと思います。実際に体感できることが大切です。
-
「プレゼン的」なプロトタイプアプローチとしては、コンセプトや背景がわかるようなイメージポスターやコンセプト動画、アイデアの文脈がわかるようなパワポの資料などがあれば良いと思います。

これらをまとめて準備できれば、十分プロトタイプとして成り立ちますし、ほとんどの人にそのアイデア価値を伝えられると思います。これを1週間程度で行い、アイデアを形にし、作っていく中でアイデア自体もブラッシュアップされていきますし、作ってみればダメだとあきらめていたアイデアが案外面白いのでは?と考えが変わったりすることがあります。
いくらコンセプトを語ってみても、目で見て、手に取って、体感してみないことには、その商品やサービスの価値は十分伝わらないということに気づかせてくれます。仮に月に2回プロトタイプを作ったら、年間24個のアイデアを作ることができてしまいます。
もちろん伝えてもその面白さが全く伝わらなかったり、認めてもらえなかったりする場合もありますが、その場合は、もしかするとそのアイデアに問題がある可能性もあるので引き返すチャンスにつながります。またいいね!ユニークだね!と伝わった場合でも、その次には「本当に売れるのか?」問題が立ちはだかるのですが、それはまた別のお話ですね。
今回は、どうアイデアを発想するか?というよりも、発想したアイデアを形にしながら膨らませたり、しぼませたりする中で、さらに発想を広げるというお話でしたが、その中でアイデアをさらに発想していくという意味では、これもまた発想法のひとつと言えるのではないでしょうか。ね!西村先生、青木先生。
ちなみに2025年には本番のプログラムが控えているそうです。ご興味があれば!
→ https://vcp.musabi.ac.jp/prototyping/
ではまた次回。今回はここまで。