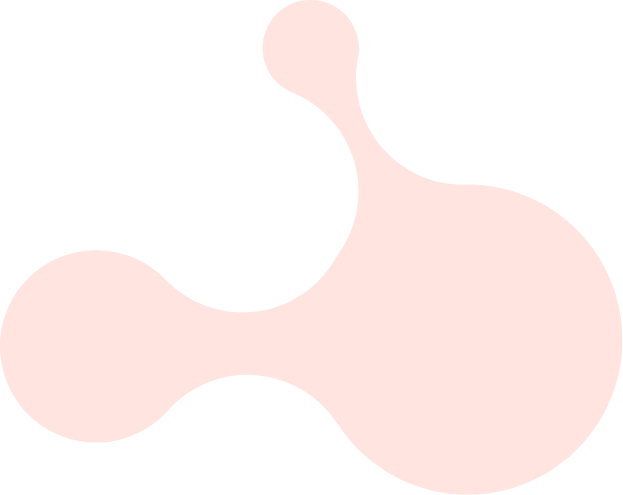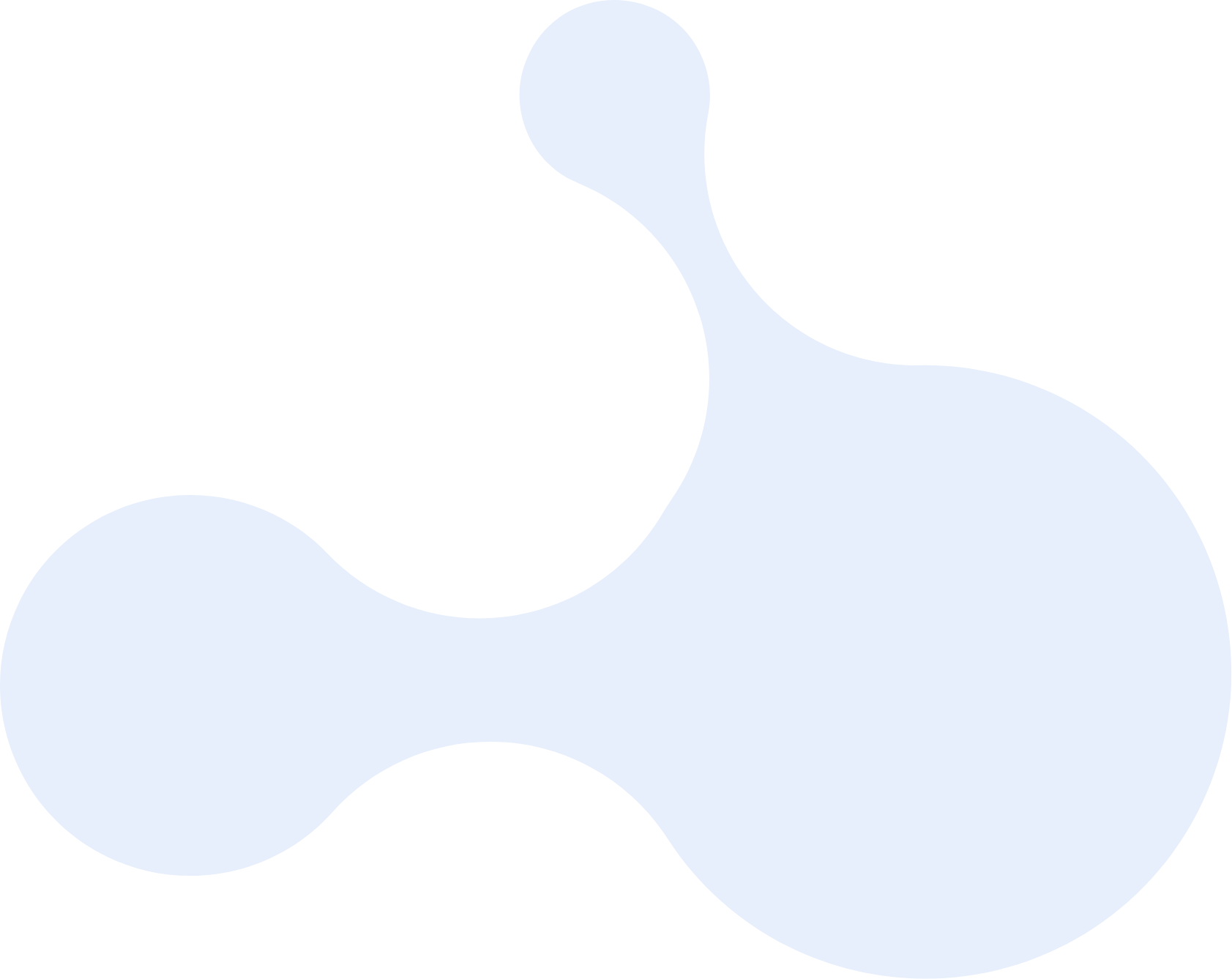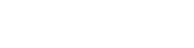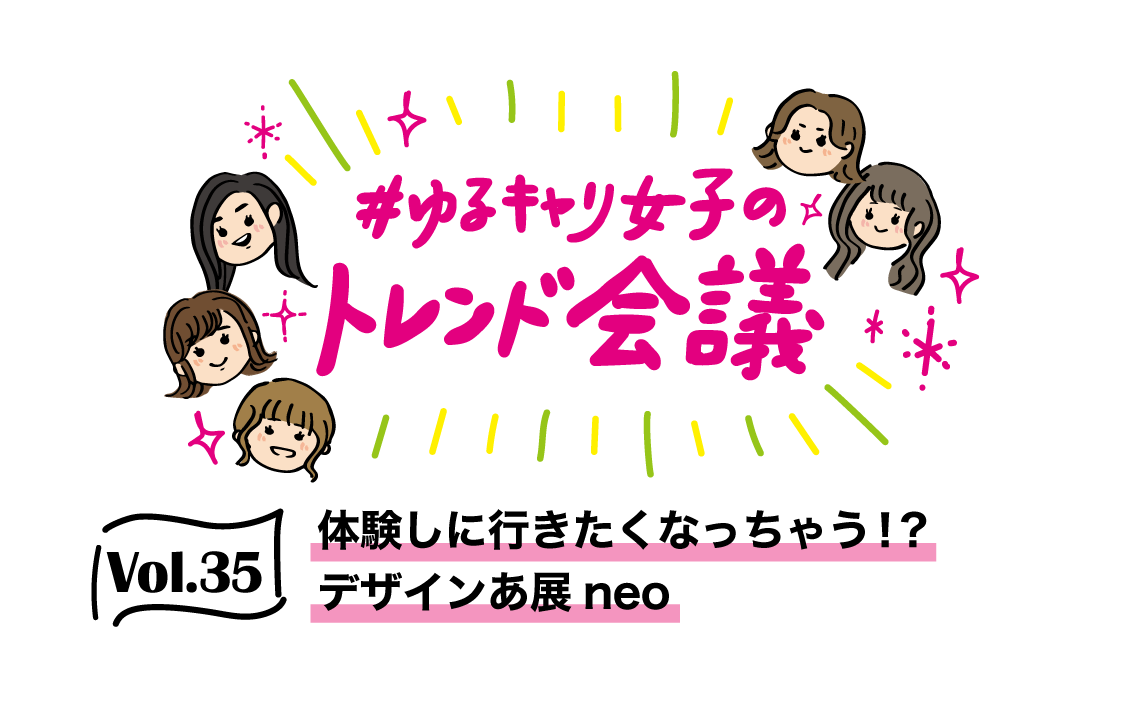主たる目的は忘れてしまおう あなたのためのアイデア発想35
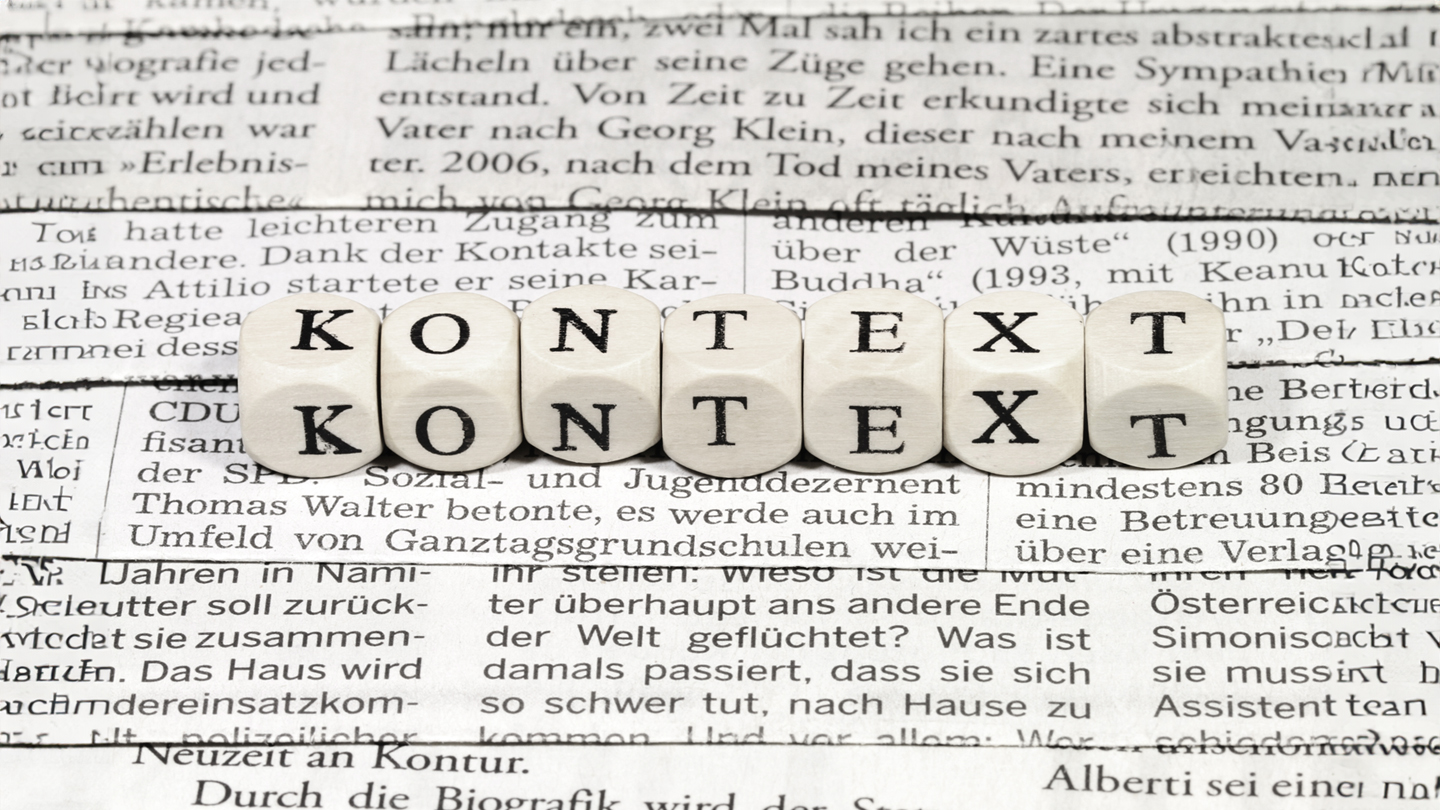
こんにちは。ホンブチョウです。この連載コラムでは私が今まで学んできたアイデア発想のやり方を毎回ひとつづつ紹介していくことで、あなたに合ったやり方を見つけてもらいたいと考えています。
第三十五回は、
文脈抽出 発想法
今回の、文脈抽出発想法とは、ある製品・サービスやテーマに対して、「主たる目的の使用シーン」ではなく、周辺の行動・タイミング・場所・感情など、“文脈”に着目し、それを意図的に抽出して発想の軸に据える方法です。
マーケティングや商品企画の世界では、「何を作るか」よりも「どんな場面で使われるか」を捉えることで、お客様との接点を考えることが多いと思います。
つまり、「製品の機能」ではなく、「文脈」にフォーカスしたアイデア発想が必要だということです。
考えるより、まずやってみましょう。
- 対象を設定する
扱う商品・サービス・体験などを明確にします。(例えば:冷凍食品/傘/ペット用品/駐車場/VR体験などです)
- 文脈を洗い出す
その対象が使われる/起こる周辺の状況を、以下のような軸で洗い出します。
- いつ(時間)• どこで(場所)• だれが(登場人物)• どういう感情で • 何と一緒に • 使用後はどうなる? • 使われないときは?• しまうときは?• 他人はどう見ているか?
(例:「傘」の場合)
- 雨の日に使う/玄関に置かれる/人混みで広げにくい/傘立てにつっこむ/忘れられやすい/雨が止むと持ち歩きに邪魔 など
- 文脈を一つ選んで抽出する
洗い出した中から、「おもしろい/まだ関心が薄く掘られていない/矛盾がある」がありそうな文脈をひとつだけ選びます。要は1つだけを切り取って、あえて“他の文脈を無視して設計する”ということになるので、そういう視点で選んでください。
- その文脈にあわせてアイデアを考える
選んだひとつの文脈、“その文脈の困りごと”だけに応える製品・サービスを構想します。
イメージしにくいと思いますので、「傘」で具体例をあげてみましょう。
「玄関に置かれる」という文脈だけに最適化された傘 → もはやインテリアと言えるようなデザインの傘
「忘れられやすい」という文脈だけに最適化された傘 → 取っ手が光って目立つ。天気予報と連携して雨が止んだら傘からお知らせが来る。
このように、「玄関に置かれる」「忘れられやすい」という主目的以外の文脈を拾うことで、まったく新しい切り口が生まれる。それが文脈抽出発想法のキモです。
他にも考えてみましょう。
本 ×「放置される」文脈だけを抽出
- 一般的な文脈:「読む」「持ち歩く」「本棚にしまう」
- 抽出した文脈:「しばらく読まれずに放置される」
- アイデア例:
→ 一定期間開かれなかった本が、表紙の色や模様が変化して“存在を訴える”機能のついた本
→ 放置時間によって物語の展開が変化するので早めに読んでみたくなる“育成型ストーリーブック”
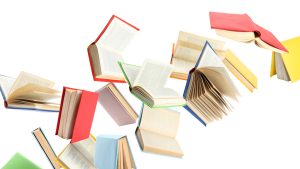
————————
冷凍食品 ×「忘れられている」文脈だけを抽出
- 一般的な文脈:「簡単に食べられる」「調理がラク」
- 抽出した文脈:「冷蔵庫の奥で忘れられる」
- アイデア例:
→ 冷凍庫をのぞいたときに「ここにいるよ!」と語りかけてくれる冷凍食品
————————
ペット用ベッド ×「掃除が大変」文脈だけを抽出
- 一般的な文脈:「快適に眠れる」「サイズ別」
- 抽出した文脈:「掃除が大変」
- アイデア例:
→ 掃除機対応の素材や、自動吸引機能付きベッド
→ 換毛期用に、天面をかんたんに張り替え可能なベッド
プロダクトやサービスが飽和した今、お客様は「差異」ではなく「納得できる背景」を求めているのかも知れません。人は“便利だから”よりも、“自分の生活に合っているから”商品を選びます。「どんな時に、それがそばにあると助かるか」という文脈とも言えます。
注意点があるとすれば、文脈を“飛び道具”にしないことです。
文脈抽出発想法は、使いこなせばユニークなアイデアがどんどん出てきます。ただ同時に、「珍しさだけ」を追いがちな落とし穴もあります。
たとえば「トイレで使うスマホ用カバー」みたいな奇をてらった商品は、確かにユニークですが“本当に欲しいか”というと難しいかも知れません。
文脈をただ“ネタ化”するのではなく、重要なのは、その文脈が「見過ごされてきたけれど、実は共感できるかも」というポイントです。「現実の行動」をイメージしつつ、その時の「感情」や、「小さな違和感」をすくいあげて考えることが大事ですね。
目の前にある日常に色々なヒントは転がっているので、「これは何のためのものか?」ではなく、「これは、どんな時に、どう使われると嬉しいのか?」と考え直すキッカケに、文脈抽出から発想することはとてもマッチしているのかも知れませんね。
ではまた次回。今回はここまで。